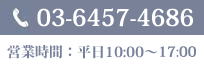企業の存在価値の追求 -盤石な経営基盤の確立4
先日、サービス業を営むある会社の社長とお会いする機会が有りました。その中で、
『会社が生き残っていくためには、何をどうすればよいのでしょうか?』と質問をいただきました。集客、人材の確保、育成、新たな事業展開、時代状況の変化への対応など様々な課題を抱える中での問いと感じました。
それに対し、生き残ることを考えるのではなく、お客様や地域から何が求められ、どういう企業が望まれているのか、所謂、存在価値を改めて確認してはどうですかとお話しをさせていただきました。